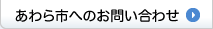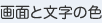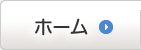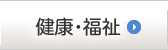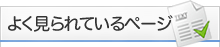国民年金保険料の免除および猶予について
保険料の免除および猶予
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合に、本人が申請し、承認を受けることによって、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
対象となる期間は、7月から翌年6月までです。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡となった場合、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますのでご注意ください。
申請する人は、年金手帳(基礎年金番号通知書)、 マイナンバーカード、本人確認書類を持って市民課へお越しください。
なお、所得の審査は、市町村民税の申告内容を基に行います。所得申告をしていない人は申請することができませんので、必ず申告してから申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする特例免除申請については、こちらの日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
これらの制度は、学生以外の人を対象としています。学生の方については、学生納付特例制度のページをご覧ください。
出産の際の免除については、こちらの日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
全額免除および一部納付(一部免除)制度
免除が認められる人
本人、配偶者および世帯主の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下の場合です。
| 種別 | 計算式 |
1カ月の保険料 (通常は17,510円) |
|---|---|---|
|
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
0円 |
|
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4,380円 |
|
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
8,760円 |
|
4分の1免除 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
13,130円 |
免除された期間分の年金額
免除を受けた期間分の年金額は、以下のように計算され、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
| 種別 | 年金 |
|---|---|
| 全額免除 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 8分の5 |
| 半額免除 | 4分の3 |
| 4分の1免除 | 8分の7 |
納付猶予制度
猶予が認められる人
50歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が、次の計算式で計算した金額以下の場合です。
計算式
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
猶予された期間分の年金額
猶予を受けた場合には、その猶予された期間は年金を受け取るための年数(10年間)には換算されますが、年金を満額受給するための期間(40年間)には算定されませんので、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
免除または猶予の承認を受けた期間の追納
納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、この期間の保険料をあとから納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
なお、保険料の追納には納付書が必要です。
納付書の発行は申し込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する福井年金事務所(0776-23-4518)までお問い合わせください。
付加年金
第1号被保険者、任意加入被保険者が毎月の保険料に付加保険料(月額400円)を追加して納付すると、年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金額(年額)
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
例えば、付加保険料を10年(400円×10年×12カ月=48,000円)
納付した場合、付加年金額は、200円×10年×12カ月=24,000円
が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
つまり、年金を2年以上受け取れば、納めた付加保険料分より多くもらえることができ、お得です。
ただし、国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を追加できませんのでご注意ください。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp