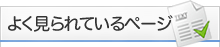認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の 1以上である住宅
減額される税額
- 居住の用に供する部分について一戸あたり120平方メートルまでを限度として、固定資産税を2分の1に減額します。
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートル超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
ただし、併用住宅の床面積のうち、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後5年度分
- 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅は、新築後7年度分
ただし、長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
申請の手続き
- 住宅を新築した翌年の1月31日までに申請してください。
申請書は下記の添付ファイル「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
- 指定確認検査機関(福井県)による認定長期優良住宅であることを証する証明書の写しを添付願います。
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp

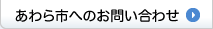

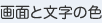






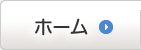

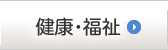




 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF形式 82キロバイト)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF形式 82キロバイト) 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(エクセル形式 18キロバイト)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(エクセル形式 18キロバイト)