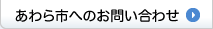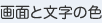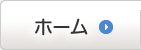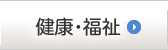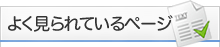令和6年12月2日で保険証の新規発行がされなくなりますので、マイナ保険証をご利用ください!
令和6年12月2日をもちまして、保険証の新規発行が終了します
お手持ちの保険証は券面の記載事項に変更がない場合、
令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。
(例:国民健康保険については、最長で令和7年7月31日まで)
※マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。
※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。
健康保険証として利用するメリット
- 医療費が節約できる
紙の保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
- より良い医療が受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※ただし、限度額適用区分が「オ」または「低2」の方で直近1年以内の入院期間が90日を超える場合は長期入院該当の申請が必要です。
利用できる医療機関・薬局に関して
以下のリンクから対象の医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードをお持ちではない方へ
市役所でマイナンバーカードの申請が必要です。詳しくは以下の市HPをご覧ください。
https://www.city.awara.lg.jp/syokai/2100/p013126.html(新しいウインドウが開きます)
マイナ保険証の利用登録方法
必要なもの
- 利用者証明電子証明書暗証番号(数字4桁)マイナンバーカード
- 「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダー」
- マイナポータルアプリのインストール
登録の流れ
マイナポータルから申請をお願いします。詳しい手順はマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
端末がない方へ
セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局、もしくは市役所の市民課で登録可能です。
スマートフォンやパソコン等の操作が不慣れな方でも健康保険証利用の申込ができるよう、市民課でサポートしております。
Q&A
Q.マイナ保険証の利用登録が完了しているかどうか知りたいです。
A.医療保険課窓口では、利用登録の確認ができません。ご自身でマイナポータルをご確認ください。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
Q.昨日、国民健康保険加入手続きをしたが、病院でオンライン資格確認をしたところ「資格なし」と表記されました。
A.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで、1周間ほどかかります。
Q.保険が切り替わったが、マイナ保険証の再登録は必要ですか?
A.自動で更新されるため、再登録は必要ありません。※国民健康保険の加入・脱退のお手続きは必要ですので、ご注意ください。
Q.オンライン資格確認で名前が●で表示されました。
A.オンライン資格確認では常用漢字ではない文字(﨑、髙など)は、●で表示される仕様となっています。
Q.高齢受給者証は廃止されますか?別途、登録は必要ですか?
A.同様に廃止される予定です。マイナ保険証の利用登録に負担割合も反映されるため、特別な手続きは必要ありません。
医療機関・薬局の方へ
オンライン資格確認を利用すると、事務手続きが簡潔になり、コスト縮減が見込まれるなどのメリットがあります。医療機関・薬局向けの案内については、次のホームページをご確認ください。
オンライン資格確認の導入について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
オンライン資格確認に関する周知素材について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一部負担金の負担割合等がオンライン資格確認の表示と保険証の表記で異なる場合は
国民健康保険の高齢受給者証(70歳~74歳の方が対象)とオンライン資格確認の一部負担金の負担割合等が異なって表示された場合は、市民課保険年金G(TEL0776-73-8015)にご相談ください。
「資格確認書」について
マイナンバーカードを保険証利用しなくても、お持ちの保険証は有効期限内であれば、これまで通り使用できます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
- 70歳以下の国民健康保険の方
お手持ちの保険証の有効期限切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を送付する予定です。
例:令和7年7月31日有効期限の場合は、令和7年7月中に「資格確認書」を送付
- 70~74歳の国民健康保険の方
高齢受給者証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ8月以降ご使用できる「資格確認書」を送付する予定です。
マイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を送付します
令和7年7月にマイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格情報のお知らせ」ではマイナ保険証をお持ちの方が、保険資格の新規取得(令和6年12月以降の加入の方)や負担割合に変更があった場合、ご自身の資格の状況がわかるお知らせとなっています。
DVや虐待などから被害支援措置を受けている方へ
情報の閲覧制限のため届出が必要です
※国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置(注釈1)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません注釈2 ※
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
加害者等から閲覧される具体例
- 加害者等が被害を受けている方のマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを使って避難先の特定につながる医療費通知情報や薬剤情報を閲覧できてしまう。
- 加害者等が医療従事者等であった場合、医療機関のシステムを使って被害を受けている方の住所等を含んだ資格情報を閲覧できてしまう。
上記のような閲覧を防ぐためには、健康保険証の発行元へ届出が必要です。
手続きなど詳しいことは、お持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。
注釈1:DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。
注釈2:国民健康保険の加入者で、支援措置を受けず閲覧制限だけを行いたい方は、資格賦課係にご相談ください。国民健康保険以外の健康保険に加入の方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)にご相談ください。
閲覧の制限を行うと
ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」および「不開示該当フラグ」の設定を行います。
- 自己情報提供不可フラグ
DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等が情報を閲覧することを防ぐことを目的として設定するものです。
※住民基本台帳支援システムに設定される「自己応答不可フラグ」とは異なります。
- 不開示該当フラグ
DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。
自己情報提供不可フラグを設定した場合
病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。
※住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に設定されます※
不開示該当フラグを設定した場合
マイナポータルでやりとり履歴が確認できなくなります。
病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が開示されません。
※住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に設定されます※
閲覧制限をかけたままマイナンバーカードでの保険証利用を行うには
国民健康保険の加入者で、以下の状況であれば届出により自己情報提供不可フラグを解除して、マイナンバーカードでの保険証利用を行うことができるようになります。
マイナンバーカードをまだ取得していない場合
届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。
解除することにより、今後マイナンバーカードを取得した場合、保険証利用登録を行うことで、病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。
有効なマイナンバーカードが手元にある場合
加害者等をマイナンバーカードの代理人として設定している場合、代理人の解除を行ってください。
解除の方法については、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
加害者等を代理人として設定していない、もしくは代理人の解除が完了した場合、届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。解除後は病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。
マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合
マイナンバーカードの一時利用停止をしたうえで、カードの再交付(有料)を行ってください。
再交付が完了したら、届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。解除後は病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。
一時利用停止の連絡先
マイナンバー総合フリーダイヤル(カードの一時停止を24時間365日受付)
0120-95-0178 (音声ガイダンス2番をお選びください)
自己情報提供不可フラグの解除届出の方法
- あわら市の国民健康保険に加入されている方
ご事情を伺い、必要書類をご案内しますので、市民課保険年金Gへご相談ください。
- 他の健康保険に加入されている方
他の健康保険に加入されている方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になったときは
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険証の発行元に解除の届出をしてください。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp