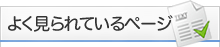あわらの民話DVDが完成しました
あわら市教育委員会では、地域の魅力の再発見を通して郷土愛を深めることを目的に、「あわらの民話DVD」を作成しました。
芦原地区、金津地区でそれぞれ10編を選定し、挿絵に福井弁の語りを重ねて、紙芝居風に仕上げています。各話の後には、その民話の発祥地の風景や地図が収められています。
(画像をクリックすると動画が流れます。)
民話一覧
| 芦原地区に伝わる民話 | 金津地区に伝わる民話 | ||
|---|---|---|---|
三枚のうろこ(番田)今から五百年程前の戦国時代、この辺りは堀江石見守ちゅう殿さまがおさめていて、お城が番田にあったんや。 |
足跡を残した幽霊(坂ノ下)昔、坂ノ下の願泉寺の坊さまが部屋で書物を読んでいたら、急に蝋燭(ろうそく)の火が揺れだしたんやって。 |
||
二面長者(二面)昔々、二面にはたいそう賢い長者さまがいたんやと。 |
吉崎のこなご(吉崎)蓮如上人さまが吉崎にお寺を立てて、説教をしなった頃、晩になると周りの村の百姓やら漁師やらが、仏の教えを聞きに来たんや。 |
||
朱ぬりのおかご(北潟)昔々、今から千年余りまえの話や。 |
馬面の赤猫(八日)昔、八日の馬面ちゅう家に、一匹の赤猫がいたんやと。 |
||
弘法の水(二面)ずーっと昔、弘法大使さまが国中を回ってなったときのはなしや。 |
嫁威し肉付きの面(嫁威)吉崎に京都から蓮如上人て言う、ほれはほれは偉い坊さまが来なって、御坊を建てたころの話や。 |
||
お筆山(浜坂)蓮如上人さまが京都から吉崎に逃げて来なった時は、みすぼらしいお姿で偉いお坊様には見えんかったんか、辺りでだれも家にお泊めするもんが無かったんやと。 |
いたずら地蔵(北稲越・菅野)昔、北稲越えのお屋敷にある大きな欅(けやき)の木の下に、地蔵があったんやと。 |
||
お不動さまの雷退治(北潟)北潟の安楽寺の垣根の近くに、幹が裂けたような一本の古い木があるんやわ。 |
娘地蔵(次郎丸)次郎丸の北側に権世川が流れてて、昔はあたり一帯に笹や雑木が生い茂り、川を渡る細い橋のまわりも草でぼうぼうやったんや。 |
||
鹿と十郷の用水(中番)平安時代の終わり頃にできた中番の春日神社には、奈良から春日明神のお神輿のお供をして、ぎょうさんの神主さんやら坊さんやらがお下りになったんやと。 |
継体天皇と剱ヵ岳(清滝)清滝の剱カ岳の頂上には、継体天皇さまをお祀りする祠があるんやって。なんでか知ってるけの。 |
||
住屋の松樹院(角屋)今から千年ほど前、比叡山の十八代目大僧正で、慈恵大師という偉いお坊さまがいたんやと。 |
七つぐろ(南稲越)昔、南稲越の西の田んぼには、所々に細長い畑があって、くろって呼ばれてたんや。 |
||
王子堂坂(舟津)ずーっと昔、後鳥羽院さまが隠岐の島に流されることになって、お后さまが後を追って渡ろうとしたらの、船が大嵐にあって三国の崎浦の浜に流れ着いたんやと。 |
お笹の池(御簾尾)昔、御簾尾のあたりの大地主やった小布施修理太夫には、お笹ちゅう名前のお妾がいたんやと。 |
||
獅子退治(田中々)ある年の正月、田中々の村道をお侍が通りかかったんやと。 |
一つ目の大男(次郎丸)昔、次郎丸から中川への道は、権世川沿いの笹の生い茂った寂しい道やったんや。 |
||
「あわらの民話DVD」は市内各図書館、公民館で貸し出しをしています。
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8041 ファックス:0776-73-1350
メール:bunka@city.awara.lg.jp

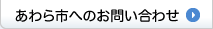

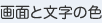






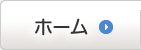

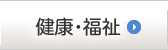











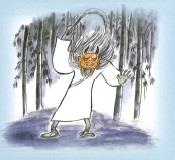


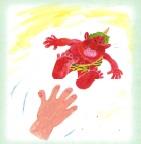




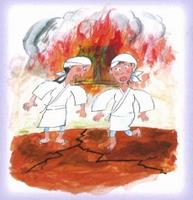
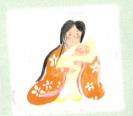



 あわらの民話DVDちらし(PDF形式 452キロバイト)
あわらの民話DVDちらし(PDF形式 452キロバイト)