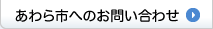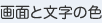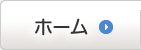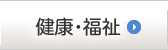マイナンバーカード(個人番号カード)関連情報
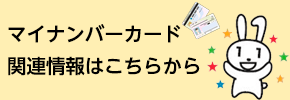
市では、行政手続の効率化と住民の利便性向上のため、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の普及を推進しています。
マイナンバーカード(個人番号カード)に対する理解を深めていただくため、関連情報を一覧にまとめています。
- はじめに:「マイナンバー制度」と「マイナンバーカード」
- マイナンバーカードでできること(公的個人認証制度、電子証明書の利用)
- マイナンバーカードを取得するには(申請と受け取り)
- マイナンバーカードの有効期限(電子証明書を含む更新の手続)
- マイナンバーカードの安全性(マイナンバーカードをなくしたとき)
- マイナンバーカードの情報の変更(住所や氏名などが変わったとき)
- 日本国外での利用について(国外転出者向けマイナンバーカード)
- 住民基本台帳カードとの関係
- よくある質問
はじめに:「マイナンバー制度」と「マイナンバーカード」
「マイナンバーカード」と「マイナンバー制度」は明確に区別されます。「マイナンバーカード」を持っていなくても、日本国内の住民は、外国人を含めて全員「マイナンバー制度」に基づく個人番号(マイナンバー)を持っており、行政手続に利用します。一方、「マイナンバーカード」はデジタル化が進む行政手続に役立つ道具であり、マイナンバーの確認や対面での本人(身元)確認のほか、ICチップに記録された電子証明書を用いてオンライン上でも本人(身元)確認ができるようになっています。
マイナンバー制度(平成28年1月1日開始)
マイナンバー制度の目的
行政事務を効率よく進めて、住民が行政手続を簡単にできるようにし、公平で公正な社会を作るために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。いわゆる「マイナンバー法」) が成立しました。この法律に基づいて、平成28年1月1日から「マイナンバー制度」が始まりました。
マイナンバー制度の概要
- マイナンバー制度開始後に、日本国内の住民全員が12ケタの個人番号(マイナンバー)を持つようになりました。
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策など、法令又は条例で定められた行政手続において利用します。
- 国や自治体などの異なる行政機関で同じマイナンバーを使うことで、住民を素早く特定し、必要なサービスを正確に届けるようにしています。また、マイナンバーを介して住民情報を行政機関同士でやり取りすることにより、異なる機関や手続ごとに必要とされていた、住民票などの書類の提出を省略することができます。
- マイナンバーを利用した行政手続きでは、本人(身元)確認を一緒に行います。このため、マイナンバーだけでは本人になりすまして行政手続を進めることはできません。
- マイナンバーは一生同じ番号を使います。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更はされません。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について(市ホームページ)
マイナンバー制度とは(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバー制度でできること(情報連携)
- 行政機関は、マイナンバーを用いた住民からの行政手続の申請に基づき、デジタル庁が運営する専用のネットワークである「情報提供ネットワークシステム」を通じて、氏名、生年月日、性別、住所に加え、社会保障制度、税制、災害対策に関する情報(例:福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうか、サービスを受けるにあたり所得はどれくらいあるか)の特定や確認(情報連携)が、迅速かつ安全に行えるようになりました。これにより、行政機関と住民の双方の労力の削減につながっています。
- 情報連携ではマイナンバー自体は利用せず、行政機関ごとに暗号化された符号を用いて連携するので、仮にマイナンバーが漏えいしても、住民の情報を芋づる式に抜き出すことはできません。この点はマイナンバーカードの安全性でも説明しています。
- 行政機関以外では、勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって税や社会保険の手続を行う場合に、勤務先や金融機関などからマイナンバーの提示を求められる場合があります。
よくある質問:マイナンバー制度について(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
自分のマイナンバーを確認するには
自分のマイナンバーを確認するには、次のような方法があります。
通知カード(令和2年5月25日廃止)
- 住民全員にマイナンバーを通知するため、平成27年10月中旬以降、国から日本国内の全世帯に「通知カード」が簡易書留により郵送されています。通知カードにはマイナンバーのほか、氏名、生年月日、性別、住所が記載され、透かしなどの偽造防止技術も施されています。ただし、身元を証明する「本人確認書類」としては利用できません。
- 通知カードは令和2年5月25日に廃止されています。通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、廃止後も引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できますが、一致していない場合には住所等を追記することはできません。
- 通知カードの再発行はできません。
通知カード(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
個人番号通知書
- 通知カード廃止後に、出生などで新しくマイナンバーを持った住民には、国と地方が共同で管理する法人である「地方公共団体情報システム機構」(新しいウインドウが開きます) からその住民の世帯主宛に「個人番号通知書」が簡易書留で送付されます。
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。 氏名、住所等に変更が生じた際にも、個人番号通知書の記載の変更は行われません。
- 個人番号通知書の再発行はできません。
個人番号通知書(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバー入りの住民票等
マイナンバーカードや、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カードがない場合などで、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、市役所窓口で「マイナンバー入りの住民票」または「マイナンバー入りの住民票記載事項証明書」をお求めいただくことになります。
なお、同一世帯のご家族がマイナンバーカードをお持ちの場合は、ご家族が自身のマイナンバーカードで本人確認を行い、「世帯の一部」として本人の住民票を請求する形で、コンビニで「マイナンバー入りの住民票」を取得することができます。
マイナンバーカードの取得
顔写真入りのマイナンバーカードを取得することで、「マイナンバーの証明」と「本人(身元)確認」を同時に行うことができます。
マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- 住民からの申請により無料で交付される、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードのおもて面は顔写真付きの「本人確認書類」として利用できます。裏面にはマイナンバーが記載されており、行政手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。
- 通知カードとは違い、取得(申請)は任意です。
- マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、ICチップに「公的個人認証制度」に基づく電子証明書を記録して利用することで、オンライン上で本人(身元)確認ができます。電子証明書の利用には「暗証番号」もしくは専用の機器による「顔認証」が必要となります。
マイナンバーカードの説明(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードでできること(公的個人認証制度、電子証明書)
「マイナンバーカード」を取得することで、以下のようなことができます。マイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書の根拠となる「公的個人認証制度」についてもこちらで説明します。
- マイナンバーを証明する書類としての利用
- 顔写真付きの公的な「本人確認書類」としての利用
- ICチップに記録される電子証明書を利用した行政手続
- その他の機能
- 暗証番号が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)について
マイナンバーを証明する書類としての利用
マイナンバーカードを窓口で提示することで、自分のマイナンバーを証明できます。これにより、一部の行政手続において行政機関同士でマイナンバー制度に基づく情報連携を行うことができるため、住民票や所得課税証明書などの書類の提出が不要になります。
顔写真付きの公的な「本人確認書類」としての利用
顔写真入りのマイナンバーカードを窓口で提示することで、運転免許証や旅券と同じように、公的な本人(身元)確認ができます。
申請時に1歳未満である場合(顔写真なしマイナンバーカード)(令和6年12月2日開始)
申請時に1歳未満である住民のマイナンバーカードには顔写真が入りません。このため、顔写真なしマイナンバーカードだけでは「本人確認書類」としては不足しますが、マイナンバーの証明や、ICチップに記録された電子証明書を用いた健康保険証としての利用などは可能です。
ICチップに記録される電子証明書を利用した行政手続
「はじめに(マイナンバーカード(個人番号カード)とは)」で述べたとおり、マイナンバーカードのICチップに記録される電子証明書を用いてオンライン上で本人(身元)確認を行うことで、市役所に行かなくても一部の行政手続ができます。
電子証明書のなりたち(公的個人認証制度)
- オンライン上で安全・確実な行政手続等を行うために、平成14年12月13日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」が成立しました。 この法律に基づいて、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための「公的個人認証制度」が始まり、制度を実現する手段として、平成16年1月29日から「電子証明書」を用いてオンライン上で本人(身元)確認を行う仕組み(公的個人認証サービス)が始まりました。
- 以上の経緯からもわかるとおり、公的個人認証制度は、マイナンバー制度やマイナンバーカードよりも前に始まったものであり、これらの制度とは独立した制度として存在していますが、電子証明書は現在はマイナンバーカードにしか記録ができないなど、相互に密接な関わりを持っています。
- 電子証明書そのものにマイナンバーは入っていないため、電子証明書を用いた本人(身元)確認にマイナンバーが使われることはありません。
- 電子証明書には「公開鍵暗号化方式」という技術が用いられており、住民それぞれのマイナンバーカードのICチップにしか入っていない固有の「鍵」を用いて、オンライン上の行政手続データや、手続ごとに生成される乱数に電子証明書を付与したものを暗号化します。暗号化の解除もこの固有の「鍵」を用いてしか行えないので、オンライン上の行政手続データや乱数及び電子証明書の暗号化の解除が送信先で問題なくできた場合、そのデータや電子証明書が固有の「鍵」を持つ本人が作成し、なりすましや改ざんを経ずに送信したものであることが証明されます。併せて、電子証明書が期限切れでないなど、有効なものであることの確認(有効性の確認)を行うことで、送信したデータが電子証明書を持つ本人が作成したものであることが公的に認められます。
- マイナンバーカード、電子証明書の発行や有効性の確認は、国と地方が共同で管理する法人である「地方公共団体情報システム機構」(新しいウインドウが開きます)が担っています。
- 電子証明書を用いて、オンライン上で行政機関が持っている自分の情報の確認や行政手続を行う窓口として、政府が運営する「マイナポータル」(新しいウインドウが開きます)があります。
- 電子証明書を用いた本人(身元)確認は、行政機関に加えて民間事業者も利用できます。
- マイナンバーカードに電子証明書の記録をしないことや、記録を抹消する(失効する)手続をすることもできます。
公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
公的個人認証ポータルサイト(地方公共団体システム機構が運営)(新しいウインドウが開きます)
マイナポータル(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
電子証明書の種類と利用可能な主な手続
公的個人認証制度に基づく電子証明書には、次の2種類があり、それぞれ以下のような手続で利用できます。
なお、電子証明書のうち「署名用電子証明書」は15歳未満の人や成年被後見人には原則発行されませんが、法定代理人が同行した上で、本人による申請がある場合等には、発行が可能です。
| No. | 電子証明書の名称 | 電子証明書に含まれている情報 | 用途と利用する主な手続 |
|---|---|---|---|
| 1 | 署名用電子証明書 |
|
オンライン上で作成したデータに付与して暗号化及び送信を行うことで、「そのデータが本人が作成した真正なものであり、本人が送信したものであること」を証明する(=電子署名を行う)ことができます。 15歳未満の人や成年被後見人には原則発行されません。 利用する主な手続としては、
|
| 2 | 利用者証明用電子証明書 |
|
手続ごとに生成される乱数に付与して暗号化及び送信を行うことで、「そのときに電子証明書を使って手続をした人が本人であること」を証明する(=本人(身元)確認を行う)ことができます。 利用する主な手続としては、
|
電子証明書を利用するには
手続において電子証明書を利用するには、まずは次のような機器にマイナンバーカードのICチップを読み取らせる必要があります。
- インターネットに接続したパソコンとICカードリーダー
- ICチップの読み取りに対応したスマートフォン
申請に利用する機器を選ぶ(公的個人認証ポータルサイト)(新しいウインドウが開きます)
- コンビニなどに設置されたマルチコピー機(証明書のコンビニ交付を利用する場合)
- 病院や薬局等に設置されたカメラ付きカードリーダー
その後、次のような方法によりICチップ内の電子証明書を利用します。
パスワード(暗証番号)の入力
- 電子証明書には任意のパスワード(暗証番号)を設定する必要があり、これをICチップを読み取る際に本人が入力を行います。
- 暗証番号は、マイナンバーカードの受け取り(交付)時などの、電子証明書を発行、記録するタイミングで本人が設定します。
- 市役所では暗証番号を保存することはありません。
- 暗証番号は電子証明書ごとに設定方法が異なります。具体的には以下の表のとおりです。
- 暗証番号の入力を一定回数間違えると、電子証明書にロックがかかり、利用ができなくなります。回数は電子証明書ごとに異なり、具体的には以下の表のとおりです。
- ロックを解除したい場合や、暗証番号を忘れてしまった場合は、市役所窓口に本人がマイナンバーカードを持参してロックの解除(暗証番号の再設定)の手続を行うか、どちらか一方の暗証番号を覚えている場合はスマートフォンアプリを利用することによりコンビニで解除(暗証番号の再設定)を行うことができます。詳しくは以下のリンク先を参照してください。
よくある質問:マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合や使えなくなってしまった場合はどうしたら良いですか? (市ホームページ)
| No. | 電子証明書の名称 | 暗証番号の設定方法 | 入力間違いによりロックがかかる回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 署名用電子証明書 | アルファベットの大文字と数字を1つ以上組み合わせた6文字以上16文字以下で設定します。 英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用できます。 (例:ABC123、A12345など) |
累計で5回 |
| 2 | 利用者証明用電子証明書 | 数字4ケタで設定します。 | 累計で3回 |
顔認証
利用者証明用電子証明書は、数字4ケタの暗証番号の入力のほか、カメラ付きカードリーダーや職員の目視による「顔認証」(本人の顔がマイナンバーカードの顔写真と同じであることを確認すること)を行うことでも利用できます。暗証番号の打ち間違いにより利用者電子証明書にロックがかかっていても、顔認証自体は利用できます。(病院や薬局等での健康保険証としての利用を行う場合)
マイナンバーカードを健康保険証利用として利用する方法(動画によるカメラ付きカードリーダーを用いた顔認証の操作の紹介)(厚生労働省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
スマホ用電子証明書搭載サービス(令和5年5月11日開始)
マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書を元に、スマートフォン専用の電子証明書(スマホ用電子証明書)を生成し、本人のスマートフォンに記録して利用することができるようになりました。(現在はAndroidスマートフォンのみで利用可能)
スマホ用電子証明書の特徴は以下のとおりです。
マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマートフォンがあれば電子証明書を利用した手続が可能
スマホ用電子証明書を記録したスマートフォンを機器等に読み取らせたり、オンライン上で作成したデータにスマホ用電子証明書を付与して送信することにより、マイナンバーカードを持ち歩かなくても、電子証明書を利用した手続の一部が行えます。利用できる手続や、対応するスマートフォンの機種については以下のリンク先をご覧ください。
スマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
よくある質問|マイナポータル:スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。(デジタル庁が運営) (新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカード、署名用電子証明書がない(失効する)とスマホ用電子証明書も生成ができない(利用ができなくなる)
スマホ用電子証明書は、スマートフォンに「マイナポータルアプリ」(新しいウインドウが開きます)をインストールし、マイナポータルアプリ上でマイナンバーカードの署名用電子証明書を読み取らせて行う「利用申請」により生成し、スマートフォンに「利用登録」(記録)を行うことで利用できるようになります。このため、スマホ用電子証明書を利用するにはまずマイナンバーカードを取得し、署名用電子証明書をマイナンバーカードに記録する必要があります。詳細な利用手順については以下のリンク先をご覧ください。
マイナポータル操作マニュアル:スマホ用電子証明書を利用する(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
また、特定の理由によりマイナンバーカードや署名用電子証明書が失効した場合、スマホ用電子証明書も連動して失効し、利用ができなくなります。
よくある質問|マイナポータル:マイナンバーカード用電子証明書とスマホ用電子証明書の違い・関係はなんですか。(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
また、有効期限到来によりマイナンバーカードの署名用電子証明書を更新した場合や、転入、転居、婚姻などに伴うマイナンバーカードの情報の変更(書き換え)に伴い署名用電子証明書の再発行を行った場合も、更新、再発行後の新しい署名用電子証明書を元に、新しいスマホ用電子証明書の利用申請を行う必要があります。
記録できるスマホ用電子証明書は2種類(マイナンバーカードの電子証明書と同様)
スマホ用電子証明書には、「スマホ用署名用電子証明書」及び「スマホ用利用者証明用電子証明書」の2種類があります。それぞれの用途やパスワード(暗証番号)の設定方法は、マイナンバーカードの署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書と同様ですが、スマホ用電子証明書のパスワードは「マイナポータルアプリ」(新しいウインドウが開きます)から本人が設定します。パスワードはマイナンバーカードの電子証明書とは異なるものを設定できます。(セキュリティの観点からも異なるものを設定することが推奨されています。)
スマホ用利用者者証明用電子証明書では、パスワード(数字4ケタ)の代わりに生体認証などが利用可能
スマホ用利用者証明用電子証明書については、パスワード(数字4ケタ)の代わりに、スマートフォンに備わっている生体認証・PIN・パターンなどによるロック解除の機能を利用することができます。利用を開始するには、パスワードの設定と同じく「マイナポータルアプリ」(新しいウインドウが開きます)から手続を行います。詳細な手順については以下のリンク先をご覧ください。
マイナポータル操作マニュアル:設定したパスワードの代わりに、生体認証などを利用する手続を行う (デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
スマホ用電子証明書を記録したスマートフォンを紛失した場合や機種変更をした場合は、スマホ用電子証明書の一時停止処理や再度の利用登録が必要
スマホ用電子証明書を記録したスマートフォンを紛失した場合や盗難に遭った場合は、悪用を防ぐため、マイナンバーカードを紛失した場合と同様、「マイナンバー総合フリーダイヤル」に連絡し、スマホ用電子証明書の「一時利用停止」を行う必要があります。
スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるときの手続(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
また、スマホ用電子証明書を記録したスマートフォンを機種変更する場合は、新しいスマートフォンで、「マイナポータルアプリ」(新しいウインドウが開きます)から「機種変更申請」を行ったうえで、再度の利用登録が必要です。詳細な手順については以下のリンク先を参照してください。
マイナポータル操作マニュアル:スマートフォンの機種変更時の手続を行う(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードのその他の機能
マイナンバーカードのICチップには、公的個人認証制度に基づく電子証明書の利用機能のほかに、次のような機能が格納されています。
券面情報
券面情報とは、マイナンバーカードの表面の情報(顔写真を含む)や裏面の情報(マイナンバーを含む)の画像データです。対面でのマイナンバーカードによる本人確認の際に、マイナンバーカードの表面の情報と一緒に確認することで、マイナンバーカードが偽造されたものでないか、マイナンバーカードの表面の情報とICチップ内の券面情報とが一致しているか(マイナンバーカードの表面の情報が改ざんされていないか)を確認することで、より確実な本人(身元)確認を行うことができます。
なお、券面情報のうちマイナンバーを除く氏名、生年月日、性別、住所、顔写真については、マイナンバーカードの表面をスマートフォンアプリやカメラ付カードリーダー等で読み取ることでも利用することができます。
券面情報による本人確認のためのアプリの一例:マイナンバーカード対面確認アプリ(デジタル庁が提供)(新しいウインドウが開きます)
市では、マイナンバーカードの券面情報とカメラ付きカードリーダーで撮影した本人の顔とを比較することによる本人確認と、券面入力補助機能を用いて申請書への氏名等の印刷が同時に行える「申請書作成補助システム(書かない窓口)」を運用しています。
住民基本台帳(住民票コード及びその入力補助機能)
マイナンバーカードのICチップには、「住民票コード」と呼ばれる11ケタの数字が記録されています。「住民票コード」はマイナンバーと同じく日本国内の住民全員が持つ番号であり、出生や入国などで初めて住民登録(住民基本台帳への登録)を行う際に生成されます。「住民票コード」を用いて、地方公共団体情報システム機構(新しいウインドウが開きます)が運営する地方公共団体専用のネットワークである「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)」上で氏名、生年月日、性別、住所とその変更情報(本人確認情報)をやり取りしています。これにより、転入や転出、婚姻などで本人確認情報に変更があった際の地方公共団体間の情報伝達が、迅速かつ安全に行えるようになっています。また、本人確認情報を法律で定められた範囲で国等に提供することにより、例えば毎年提出の必要があった年金の現況届が不要になるなど、国や地方公共団体、住民の双方の労力の削減につながっています。
なお、マイナンバーは「住民票コード」を元に住基ネットを経由して生成されるものであり、地方公共団体に限らず、国などへの行政手続において共通に使える番号という点で住民票コードとは異なります。
住基ネットについて(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードに記録された住民票コードは、転入や転出、婚姻などで本人確認情報に変更があった場合に、窓口でマイナンバーカードの情報の書き換えを行う際に利用します。利用には、マイナンバーカードの受け取り(交付)時などに設定する暗証番号(数字4ケタ)が必要になります。暗証番号は電子証明書(No.2の利用者証明用電子証明書)の暗証番号や、No.4の券面事項入力補助用暗証番号と同じ数字を設定することもできます。また、電子証明書と同様、市役所では暗証番号を保存しません。
| No. | 名称 | 用途と利用する主な手続 | 暗証番号の設定方法 | 入力間違いによりロックがかかる回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 住民基本台帳用暗証番号 | 住民票コードをテキストデータとして抽出し、住基ネットの事務に利用します。 市においては、引っ越し等によるマイナンバーカード内のデータの書き換えを行う際の、住民による市のパソコンへのログイン時に使用します。 |
数字4ケタで設定します。 | 累計で3回 |
券面事項入力補助機能
マイナンバーカードの券面情報のうちマイナンバー、氏名、生年月日、性別、住所(券面事項)をテキストデータとして抽出し、オンライン申請等での情報の転記に利用します。マイナンバーを含む券面事項を利用するには、マイナンバーカードの受け取り(交付)時などに設定する暗証番号(数字4ケタ)が必要になります。暗証番号は電子証明書(No.2の利用者証明用電子証明書)の暗証番号や、No.3の住民基本台帳用暗証番号と同じ数字を設定することもできます。また、電子証明書と同様、市役所では暗証番号を保存しません。
| No. | 名称 | 用途と利用する主な手続 | 暗証番号の設定方法 | 入力間違いによりロックがかかる回数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 券面事項入力補助用暗証番号 | マイナンバー、氏名、生年月日、性別、住所(券面事項)をテキストデータとして抽出し、オンライン申請等での情報の転記に利用します。 一例としては次の手続があります。
|
数字4ケタで設定します。 | 累計で3回 |
なお、券面事項のうちマイナンバーを除く氏名、生年月日、性別、住所については、マイナンバーカードの表面をカメラ付カードリーダー等で読み取ることでも利用することができ、これを用いたサービスとして、市ではマイナンバーカードの券面事項の申請書への印刷が行える「申請書作成補助システム(書かない窓口)」を運用しています。
暗証番号が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)について
上記の暗証番号の管理に不安がある人のために、マイナンバーカードの受取などの際に手続きをいただくことで、暗証番号がいらないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)を作ることができます。 顔認証マイナンバーカードはいわば通常のマイナンバーカードの機能限定版であり、以下のような制限があります。
- No.1の署名用電子証明書は使えません。(カードに記録されません。)
- No.2の利用者証明用電子証明書の暗証番号は使えなくなり、顔認証でのみ利用できます。カメラ付きカードリーダーを用いた病院や薬局等での健康保険証としての利用は顔認証によりできますが、マイナポータル(新しいウインドウが開きます)等のウェブサイトへのログインや証明書のコンビニ交付など、暗証番号の使用を伴うサービスはすべて利用できません。
顔認証マイナンバーカードへの変更手続の方法など、詳しい情報は以下のリンク先を参照してください。
なお、顔写真なしマイナンバーカードは顔認証が使えないことから、顔認証マイナンバーカードへの変更はできません。
よくある質問:暗証番号がいらないマイナンバーカードを作るにはどうしたら良いですか? (市ホームページ)
マイナンバーカードを取得するには(申請と受け取り)
マイナンバーカードを取得するには、地方公共団体情報システム機構(新しいウインドウが開きます)に申請を行い、完成したカードの受け取りを行う必要があります。マイナンバーカードは地方公共団体システム機構で発行され、市役所に届いた後に受け取りの通知を本人の住所宛に転送不要郵便で送付します。このため、申請から受け取りまでは約1カ月を要しますが、特定の条件に当てはまる人は、申請から1週間前後を目安に、マイナンバーカードを地方公共団体システム機構から本人の住所宛に直接「簡易書留」で送付する「特急発行申請」が利用できます。
申請や受け取りの種類や方法については以下をご覧ください。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードを申請するには、まず「個人番号カード交付申請書」がお手元にあるかどうかを確認してください。
個人番号カード交付申請書は、「マイナンバー制度」と「マイナンバーカード」で説明のあった、マイナンバーを住民に通知するために送付される「通知カード」(新しいウインドウが開きます)もしくは「個人番号通知書」(新しいウインドウが開きます)に付属している申請書になります。交付申請書には、氏名や住所などの情報のほか、通常であれば「申請書ID」と呼ばれる23ケタの数字と、オンライン申請用の二次元コードが印刷されています。
個人番号カード交付申請書がお手元にない場合や、交付申請書に申請書IDやオンライン申請用の二次元コードが入っていない場合は、下記リンク先を参照いただくか、市民課窓口グループまでお問い合わせください。交付申請書の内容についてもリンク先に掲載されていますので、参考にしてください。
よくある質問:マイナンバーカード交付申請書を紛失しました。申請するにはどうすればいいですか? (マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
自分で申請する
個人番号カード交付申請書がお手元にある場合は、以下の方法によりご自分でマイナンバーカードを申請できます。
オンラインで申請する
個人番号カード交付申請書と、スマートフォンやインターネットに接続されたパソコン等を用いて、時間や場所に関係なくオンラインで申請が行えます。
- オンライン申請用の二次元コードをスマートフォンで読み取らせる、もしくは申請書IDをマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構が運営)(新しいウインドウが開きます)に入力します。
- 申請用URLを通知するためのメールアドレスを登録します。
- 登録メールアドレスに申請用URLが届いたら、顔写真をアップロードします。(申請者が1歳未満である場合は、顔写真の登録は不要です。)
申請用URLの通知メールは「迷惑メール」として別のフォルダに格納されてしまうことがありますので、時間が経過しても届かない場合は、迷惑メールの中を探してみてください。 - 生年月日、電子証明書の利用希望の有無、点字(マイナンバーカード表面に氏名ふりがなの点字の凹凸の追加)の希望の有無を入力し、申請を完了します。
- 申請完了後、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届きます。
スマートフォンやパソコンによる申請(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
郵送で申請する
個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、写真を添付して郵送で申請が行えます。
交付申請書への記入方法や顔写真のチェックポイント、送付用封筒のダウンロードは下記リンク先をご覧ください。
郵送による申請(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
証明写真機で申請する
対応している証明写真機に個人番号交付申請書の二次元コードを読み取らせ、必要事項を入力することで、証明写真機で写真を撮影して申請が行えます。
まちなかの証明写真機での申請(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
出張申請を利用する
個人や企業、団体からの申込により、ご自宅や事業所に職員が出向いて申請を受け付ける「出張申請」を行っています。「本人確認書類」や「通知カード」(新しいウインドウが開きます)などを事前にご準備ください。
- 申込は、市民課窓口グループで随時受け付けています。窓口、電話、メールのほか、電子申請(新しいウインドウが開きます)でも受け付けています。(日程調整のため、出張申請の実施の候補日を複数お伝えください。)
- 個人番号カード交付申請書がお手元になくても申込が可能です。(申込の際にお持ちでない旨をお伝えください。)
- 職員が写真を無料で撮影します。
- 特定の「本人確認書類」や「通知カード」(新しいウインドウが開きます)などが一通り揃っている場合は、申請した本人の住所宛に「本人限定郵便」でマイナンバーカードが郵送できます。(市役所に受け取りに来る必要がなくなります。)(申込の際にどのような書類がお手元にあるかをお伝えください。)
- 「本人限定郵便」でマイナンバーカードを郵送する場合は、申請時にあらかじめ電子証明書の暗証番号(No.1、No.2)やマイナンバーカードの暗証番号(No.3、No.4)を設定していただきます。
出張申請の申込方法や必要となる書類については下記リンク先をご覧ください。
市役所市民課、市民課芦原分室で申請する
市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)で、営業時間中は随時マイナンバーカードの申請を受け付けています。「本人確認書類」や「通知カード」(新しいウインドウが開きます)などを市民課または芦原分室にお持ちください。
- 個人番号カード交付申請書がお手元になくても申請受付が可能です。
- 職員が写真を無料で撮影します。
- 出張申請と同じく、特定の「本人確認書類」や「通知カード」(新しいウインドウが開きます)などが一通り揃っている場合は、申請した本人の住所宛に「本人限定郵便」でマイナンバーカードが郵送できます。(市役所に受け取りに来る必要がなくなります。)(どのような書類が必要になるかは、下記リンク先を参照いただくか、市民課窓口グループにお尋ねください。)
- 「本人限定郵便」でマイナンバーカードを郵送する場合は、申請時にあらかじめ電子証明書の暗証番号(No.1、No.2)やマイナンバーカードの暗証番号(No.3、No.4)を設定していただきます。
- 市役所市民課のみ、延長窓口で申請受付ができるほか、休日申請・交付窓口も「完全予約制」により利用できます。
市役所での申請のご案内は「出張申請受付」のページ(下記リンク先)に併せて掲載していますので、ご覧ください。必要となる書類についても出張申請と同じです。
市役所でも申請を受け付けています。(マイナンバーカード出張申請受付について(市ホームページ)内)
特急発行申請を利用する
マイナンバーカードを紛失した、出生届により住民登録をしたなど一定の条件を満たした場合、申請から1周間前後を目安に、地方公共団体システム機構からマイナンバーカードを本人の住所または指定した送付先宛に直接「簡易書留」(新しいウインドウが開きます)で送付する「特急発行申請」が利用できます。
- 原則、市役所などでの本人との対面による申請受付になります。(例外として、出生届と同時に申請書を提出する場合は本人との対面は不要です。)
- 出張申請と組み合わせて申請することもできます。(申込の際に特急発行申請を希望する旨をお伝えください。)
- 職員が写真を無料で撮影します。
- 申請時にあらかじめ電子証明書の暗証番号(No.1、No.2)やマイナンバーカードの暗証番号(No.3、No.4)を設定していただきます。
- 「本人確認書類」をマイナンバーカードごと紛失したなどで不足があるなどの理由により、簡易書留でのマイナンバーカードの送付ができない場合があります。この場合は市役所市民課での受取になります。
特急発行申請が可能となる条件や申込方法、必要書類については、以下のリンク先をご覧いただくか、市民課窓口グループにお尋ねください。
特急発行・交付制度による申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受け取り方法は次のようなものがあります。申請の状況によってはご希望の受け取り方法を選択できないのでご注意ください。
市役所市民課、市民課芦原分室で受け取る(所要時間:15分程度)(予約優先)
マイナンバーカードを自分で申請した人のマイナンバーカードの受け取りは、申請した本人と職員が対面して本人(身元)確認を行う必要があるため、市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)での対面での受け取りになります。
地方公共団体システム機構からマイナンバーカードが市役所に届いたら、受け取りの通知として「マイナンバーカード交付通知書」(はがき)を本人の住所宛に転送不要郵便で送付します。はがきが届いたら、市役所市民課もしくは市民課芦原分室(あわら市保健センター内)のどちらが受取場所になっているかを確認いただいた後、受取日時をご予約のうえ、はがきと必要書類を持参し、マイナンバーカードをお受け取りください。
受け取りには15分程度の時間を要するため、受取予約をした人から優先して交付(受け取り)の手続きを行います。予約をしていない人は、予約をした人の交付が終わるまで手続きをお待ちいただくことになりますので、ご了承ください。
交付通知書(はがき)の内容や必要書類の詳細は次のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受け取り)について(市ホームページ)
マイナンバーカードを受け取る(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
本人限定郵便で受け取る(出張申請、市役所で申請した場合)
出張申請もしくは市役所で一度職員と対面してマイナンバーカードを申請している場合で、「本人確認書類」等が一通り揃っていた場合は、申請した本人の住所宛に「本人限定郵便」(新しいウインドウが開きます)でマイナンバーカードを郵送できます。(市役所に受け取りに来る必要はありません。)
「本人限定郵便」(新しいウインドウが開きます)でのマイナンバーカード受取の大まかな流れは以下のとおりです。マイナンバーカードが本人宛に直接届くわけではなく、まずは郵便局から「到着通知書」が本人の住所宛に送付されます。(宅配便の不在通知により再配達を申請するようなイメージです。)
- 郵便局から「到着通知書」が本人の住所宛に送付されます。
- 「到着通知書」の案内に従い、二次元コードによるオンライン申請や電話等で、ご自宅で受取可能な日・時間帯を指定します。 (夜間、休日も指定が可能です。)また、ご自宅での受取の際に、配達員に提示いただく「本人確認書類」の種類(運転免許証、資格確認書等)を併せて指定します。
- 指定した日時にご自宅にマイナンバーカードが配達されますので、「本人確認書類」を配達員に提示してカードの受取を行ってください。
- 本人限定郵便で発送したマイナンバーカードには、出張申請もしくは市役所での申請時にあらかじめ設定した暗証番号が記録されていますので、届いたその日から利用できます。
- 郵便局に「到着通知書」と「本人確認書類」を持参して、郵便局でマイナンバーカードを受け取ることもできます。
- 本人限定郵便は郵便局での保管期限があり「到着通知書」に明示されています。保管期限を過ぎると市役所にマイナンバーカードが返送されてしまうので、ご注意ください。
簡易書留で受け取る(特急発行申請を利用した場合)
特急発行申請によりマイナンバーカードの申請を行った場合で、「本人確認書類」等の条件を満たした場合は、申請から1周間前後を目安に、申請した本人の住所または指定した送付先宛に「簡易書留」(新しいウインドウが開きます)でマイナンバーカードが地方公共団体システム機構から直接郵送されます。(市役所に受け取りに来る必要はありません。)
- 本人以外のご家族でもサイン等により受取が可能です。また、戸建住宅の宅配ボックスへの配達も可能です。
- 休日にも配達が可能です。
- 不在のため配達できなかった場合は、郵便局に希望する日・時間帯を指定することで、再配達が可能です。また、戸建住宅の宅配ボックスがある場合は宅配ボックスに配達します。
- 配達できなかった簡易書留は郵便局での保管期限があります。保管期限を過ぎると市役所にマイナンバーカードが返送されてしまうので、ご注意ください。
代理人が受け取る
市役所でマイナンバーカードを受け取る場合は、本人による受け取りが原則ですが、入院や施設入所、身体の障害など、やむを得ない理由により来庁が難しい場合に限り、代理人が受け取ることが可能です。
代理人が受け取る場合に必要な書類は、市役所で本人が受け取る場合と異なり、本人が自分の意志で申請した旨を回答した「回答書」に加え、「委任状」や「電子証明書(No.1、No.2)やマイナンバーカード(No.3、No.4)の暗証番号の記入」(「マイナンバーカード交付通知書」(はがき)に記入欄が設けられています。暗証番号は目隠しシールの記入欄への添付や封筒への封入など、職員以外に見られることのないようにする必要があります。)、本人の顔写真入りを含む「複数の本人確認書類」、「来庁が困難であることが客観的に分かる書類」などが追加で必要になります。
代理受取が可能な条件や、必要な書類等の詳細は、下記リンク先の「マイナンバーカードの受け取りについて」の案内ページに併せて掲載していますので、ご覧ください。
代理人が受け取る場合(「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受け取り)について」(市ホームページ)内)
マイナンバーカードの発行状況を確認する
マイナンバーカードの申請後、「マイナンバーカード交付通知書」(はがき)が届かないことなどの理由でカードの発行状況を確認したい場合は、個人番号カード交付申請書に記載の「申請書ID」(23ケタの数字)と生年月日を「マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構が運営)」(新しいウインドウが開きます) 内の以下のリンク先で入力することにより、オンラインで発行状況を確認できます。
マイナンバーカード申請状況照会サービス(マイナンバーカード総合サイト内)(新しいウインドウが開きます)
- 発行状況の確認が可能になるまでには申請日から2、3日かかりますので、申請直後の場合は後日もう一度お試しください。
- 「申請書ID」が分からない場合は、市民課窓口グループまでお問い合わせください。
マイナンバーカードの有効期限(電子証明書を含む更新の手続)
マイナンバーカードや電子証明書には「有効期限」があり、一般に「発行してから回目の誕生日」というように決められています。
有効期限が切れたマイナンバーカードは、「本人確認書類」として利用することができなくなるほか、電子証明書の有効期限が切れたマイナンバーカードは、病院や薬局等での健康保険証としての利用をはじめとした電子証明書を利用したサービスが使えなくなるため、これを更新する手続きが必要となります。
- 有効期限の確認方法
- 有効期限の決め方について
- 有効期限が到来した電子証明書やマイナンバーカードの更新手続
- 外国人住民で在留期限のある人のマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限の変更及び特例延長手続
有効期限の確認方法
- マイナンバーカードの有効期限は、カード表面の右側に「印刷」されています。
- 電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの有効期限のすぐ下の欄に「手書き」で記載されています。(記載がない場合もあります。)
具体的な位置は以下の画像のとおりです。
有効期限の決め方について
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限の長さは本人の状況によって異なります。具体的な決め方は次のリンク先にある一覧のとおりですが、一般に日本人住民のマイナンバーカードの有効期限は「発行してから10回目の誕生日(18歳以上の人の場合)もしくは5回目の誕生日(18歳未満の人の場合)」となり、電子証明書の有効期限は、一律「発行してから5回目の誕生日」になります。
これは、マイナンバーカードにおいては、年数の経過により顔が変化すること、電子証明書においては、技術の進歩に伴い電子証明書の持つセキュリティ技術もその都度新しいものに変えていく必要があることを理由としています。
マイナンバーカード等の有効期間(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
例として、18歳以上の日本人住民の場合は「マイナンバーカード自体は発行してから10回目の誕生日まで有効であるが、マイナンバーカードの有効期間中の5回目の誕生日に一度電子証明書の有効期限が到来する」ということになります。電子証明書の有効期限が到来した際は、送付される案内に従い、市役所で電子証明書の更新手続を行います。この場合、一度更新した電子証明書の新たな有効期限は、更新してから5回目の誕生日(マイナンバーカードの有効期限を超えない日まで)になるので、実質的にマイナンバーカードの有効期限と同じになります。
その後、マイナンバーカードの有効期限が到来した際には、送付される案内に従い、マイナンバーカードの更新手続を行います。マイナンバーカードの更新手続の流れは通常のマイナンバーカードの申請(初めてカードを申請する場合)と同じであるため、併せて送付された「個人番号カード交付申請書」を用いて、市役所に行かなくても自分で新しいカードの申請をすることができます。
なお、外国人住民のうち永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間は日本人住民と同じになります。それ以外の人で在留期限のある人のマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限は「在留期限と同じ」になりますが、以下のリンク先でも説明があるとおり、在留期限の延長申請を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限も新しい在留期限に応じて変更または特例による延長を行う必要があります。
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
有効期限が到来した電子証明書やマイナンバーカードの更新手続
電子証明書やマイナンバーカードの有効期限の2、3ヶ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(新しいウインドウが開きます)から「有効期限通知書」が送付されます。有効期限通知書内には更新が必要な手続きの種類(発行してから5回目の誕生日が到来することによる電子証明書単独の更新か、10回目(18歳未満の住民の場合は5回目)の誕生日が到来することによる電子証明書とマイナンバーカードの両方の更新か)が記載されており、手続きの種類に応じて封入されている書類や案内が異なります。
有効期限通知書の案内に従って、電子証明書の更新手続もしくはマイナンバーカードの更新手続を行ってください。更新手続にかかる手数料はいずれも無料ですが、マイナンバーカードの更新手続を経て新しいカードを受け取る際に、現在使用しているカードを返納できない(受け取る際に持参しない)場合は、紛失扱いとなり「再交付手数料」を頂くことになりますので、ご注意ください。
有効期限通知書や封入されている書類の具体的な内容は以下のリンク先をご覧ください。
更新手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
電子証明書の更新手続(所要時間:15分程度)
電子証明書の更新手続の大まかな流れは以下のとおりです。
- 有効期限通知書が届いたら、中身を確認のうえ、マイナンバーカード及び暗証番号(マイナンバーカードを取得した際に設定した、(No.1)署名用電子証明書暗証番号及び(No.2)利用者証明用電子証明書暗証番号や、(No.3)住民基本台帳用暗証番号をご準備のうえ、市役所市民課もしくは市民課芦原分室(あわら市保健センター内)に更新手続きにお越しください。
- 市備え付けの「電子証明書の更新申請書」を記入いただいた後、暗証番号を市のパソコンに入力していただき、電子証明書の更新処理を行います。
- 更新後、職員によるチェックや新しい有効期限の記入を経て、マイナンバーカードをお返しします。
- 電子証明書の有効期限が切れてしまった場合でも更新は可能です。
- 電子証明書の更新手続は原則本人が行う必要がありますが、以下の書類を本人が準備し、代理人に持参してもらうことで、代理人による更新手続が可能です。代理人による更新手続では、以下の書類に基づき職員が暗証番号の入力を含めた更新処理を行います。
- 有効期限通知書に同封された「回答書兼委任状」に、本人が自分の住所及び氏名、代理人の住所及び氏名、暗証番号を記入し、代理人に見られないよう、併せて同封された封筒に封入封かんしたもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真入りの「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 本人が更新手続を行う際、電子証明書の暗証番号を忘れた、もしくは電子証明書にロックがかかってしまっている場合は、 手続と同時に暗証番号の再設定を行うことができます。ただし、代理人が更新手続を行う際は、暗証番号の再設定はその場で行うことはできません。後日、本人への照会等やを経て改めて手続を行っていただくことになりますので、ご注意ください。
- 電子証明書の更新後は、新しい電子証明書と国や市の持つシステムとの連携に時間を要することにより、 しばらくの間利用できなくなる手続があります。また、更新後の新しい電子証明書を再度登録、もしくは再度申請しないと利用できない手続やサービスもあります。それぞれの手続やサービスは主に以下のとおりです。
| 手続名称 | 利用する電子証明書 | 利用できない期間(目安) | 説明または説明へのリンク先 |
|---|---|---|---|
| マイナポータル(新しいウインドウが開きます)へのログイン | (No.2)利用者証明用電子証明書 | 更新から1時間 | よくある質問|マイナポータル:マイナポータルへログインしようとすると「本人確認情報が一致しませんでした。(エラー番号:ED1108)」というメッセージが表示され、ログインできない (デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます) |
| 病院や薬局等での健康保険証としての利用(申込) | (No.2)利用者証明用電子証明書 | 更新から最短1時間、最長翌朝9時以降 | よくある質問|マイナポータル:マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新をしました。更新してすぐにマイナンバーカードの健康保険証等利用の申込はできますか。利用登録が完了するまでにかかる時間を教えてください。 (デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます) |
| 証明書のコンビニ交付 | (No.2)利用者証明用電子証明書 | 最長1日間 | (No.2)利用者証明用電子証明書のシリアル番号を個人識別に使用しており、シリアル番号の変更を伴う電子証明書更新後は、更新から使えるようになるまで時間差が生じます。 |
| 手続、サービスの名称 | 再度登録が必要な電子証明書 | 説明または説明へのリンク先 |
|---|---|---|
| e-Taxを利用した確定申告(新しいウインドウが開きます) | (No.1)署名用電子証明書 | 電子証明書の更新後は、手動でe-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」→「電子証明書登録・更新」から新たに取得した電子証明書を登録する必要があります。 よくある質問:電子証明書が有効期限切れとなった場合には、どうすればいいですか。 (e-Taxウェブサイト) (新しいウインドウが開きます) |
| スマホ用電子証明書搭載サービス | (No.1)署名用電子証明書を元に生成される新しいスマホ用電子証明書 | 電子証明書の更新後は、ご自身のスマートフォンにインストールした「マイナポータルアプリ」(新しいウインドウが開きます)に、更新後の新しい(No.1)署名用電子証明書を記録したマイナンバーカードを読み取らせたうえで、スマホ用電子証明書の更新・再発行申請を行う必要があります。 マイナポータル操作マニュアル:スマホ用電子証明書の更新・再発行の利用申請を行う (デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます) |
| 証明書のコンビニ交付のうち「本籍地証明書交付サービス」 (新しいウインドウが開きます) | (No.2)利用者証明用電子証明書 | (No.2)利用者証明用電子証明書のシリアル番号を本籍地の戸籍との紐付けに使用しており、シリアル番号の変更を伴う電子証明書更新後は、再度コンビニ内の「マルチコピー機」等から利用登録申請(コンビニ交付ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)を行う必要があります。 |
マイナンバーカードの更新手続
マイナンバーカードの更新手続の大まかな流れは以下のとおりです。
- 有効期限通知書が届いたら、「個人番号カード交付申請書」(通常のマイナンバーカードの申請(初めてカードを申請する場合)と同様の、本人の情報及び「申請書ID」と呼ばれる23ケタの数字と、オンライン申請用の二次元コードが印刷されているもの)が同封されているかご確認ください。
- 申請書IDや二次元コード入りの交付申請書がある場合は、初めてマイナンバーカードを申請する場合と同様に、自分で、または出張申請を利用して、もしくは市役所で顔写真を撮影して、新しいマイナンバーカードを申請することができます。ただし、特急発行申請は利用できません。(有効期限到来による更新は特急発行申請の対象外となります。)
- 新しいカードが完成した際の受け取りについても、初めてマイナンバーカードを申請する場合と同様、申請方法に応じた受取方法を選択できますが、本人限定郵便によりカードを受け取る場合は、申請時に現在のマイナンバーカードを(有効期限が切れていなくても)返納いただく必要がありますので、利便性を勘案のうえ受取方法をご検討ください。
外国人住民で在留期限のある人のマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限の変更および特例延長手続
外国人住民で在留期限のある人が、在留期限の延長申請を行った場合は、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限も新しい在留期限に応じて変更または特例による延長を行う必要があります。日本人住民などの場合と異なり、「有効期限通知書」は送付されませんので、ご注意ください。
変更または延長手続を行わずに現在のマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合は、紛失等によりマイナンバーカードの再発行を行う場合と同様、新しいカードの受け取りの際に「再交付手数料」を納めていただくことになりますので、重ねてご注意ください。
外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
在留期限の延長に伴うマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限の変更(所要時間:15分程度)
在留期限の延長を経て新しい在留カードがお手元にある場合で、マイナンバーカードが有効期限内である場合は、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留カードの有効期限に応じて変更することができます。(変更後の有効期限は日本人と同じく、最長で10年間です。)有効期限の変更の大まかな流れは以下のとおりです。
- 新しい在留カードと、現在のマイナンバーカード(有効期限内のもの)及び暗証番号(マイナンバーカードを取得した際に設定した、電子証明書の暗証番号(No.1、No.2)や住民基本台帳用暗証番号(No.3)をご準備のうえ、市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)に有効期限の変更申請にお越しください。
- 市備え付けの「在留期間更新伴う有効期間変更申請書兼電子証明書発行/更新申請書」を記入いただいた後、暗証番号を市のパソコンに入力していただき、有効期間の変更処理と電子証明書の更新処理を行います。
- 変更処理後、職員によるチェックや新しい有効期限の「券面記載欄」への記入を経て、マイナンバーカードをお返しします。
- 代理人によるマイナンバーカードの有効期限の変更申請も、以下の書類等を準備し、代理人が持参することで受付はできますが、電子証明書の有効期限の変更は本人しか行うことができないため、後日、本人が改めて手続きにお越しいただくなどの対応が必要になります。
- 本人が記入、または記名押印を行った代理人選任届(いわゆる「委任状」):市備え付けの様式は、各種証明書の交付申請のページをご参照ください。
- 本人の新しい在留カード
- 本人のマイナンバーカード及び(No.3)住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 代理人の顔写真入りの「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証等)
在留期限の延長(更新中であること)を理由としたマイナンバーカードの有効期限の特例による延長(所要時間:15分程度)
在留期限の延長の申請はしているものの、マイナンバーカードの有効期限までに在留期間延長の許可が下りない(新しい在留カードが届かない)場合は、特例としてマイナンバーカードの有効期限を2カ月間延長することができます。この手続きを経て延長した期間中に新しい在留カードが届いたら、改めて有効期間の変更を行っていただく必要があります。有効期限の特例による延長の大まかな流れは以下のとおりです。
- 現在の在留カードの裏面に「有効期間更新許可申請中」のスタンプが押されたもの、もしくは「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメール(オンラインで更新申請をしている場合)のどちらかと、現在のマイナンバーカード(有効期限内のもの)及び暗証番号(マイナンバーカードを取得した際に設定した、電子証明書の暗証番号(No.1、No.2)や住民基本台帳用暗証番号(No.3)をご準備のうえ、市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)に有効期限の特例による延長の申請にお越しください。
- 市備え付けの「在留期間更新伴う有効期間変更申請書兼電子証明書発行/更新申請書」を記入いただいた後、暗証番号を市のパソコンに入力していただき、有効期間の特例による延長処理と電子証明書の更新処理を行います。
- 延長処理後、職員によるチェックや延長された有効期限の「券面記載欄」への記入を経て、マイナンバーカードをお返しします。
- 代理人によるマイナンバーカードの特例による延長申請も、代理人選任届等、有効期間の変更の場合と同様の書類の追加持参により受付が可能です。
マイナンバーカードの安全性(マイナンバーカードをなくしたとき)
マイナンバーカードの「安全性」は、法令をはじめとして、セキュリティ技術や職員による運用など、さまざまな面から対策がなされていますが、この「安全性」についても「はじめに」で示したとおり「マイナンバー制度」と「マイナンバーカード」とで区別して認識することで、より理解が深まると考えられます。
また、安全性が問われる場面としての「マイナンバーカードをなくしたとき」の対応や、その後の手続についてもこの項目で説明します。
- マイナンバー制度における安全対策
- マイナンバーカードにおける安全対策
- マイナンバーカードをなくしたとき(一時停止と再発行手続)
- 昨今発生している「マイナンバーの紐付け誤り」、「コンビニでの証明書の誤交付」、「なりすまし」などのトラブルはマイナンバーカードが原因ではありません
- マイナンバーに便乗した詐欺にご注意ください
マイナンバー制度における安全対策
マイナンバーの利用、収集、保管の制限
- マイナンバーの利用(マイナンバー制度に基づく情報連携などを含む)が可能な行政手続は、法令または条例で定められています。
- マイナンバーを含む個人情報を収集したり保管したりすることは、法令または条例に規定がある行政手続を行う場合に制限されています。手続の代表的な例としては社会保障、税、災害対策などの手続があり、これらの手続を進めるために、行政機関、勤務先、金融機関からマイナンバーの提供を求められますが、法令または条例に規定されていない手続で提供を求められることはありません。
マイナンバーだけでは本人になりすまして行政手続を進めることはできない
マイナンバー制度の説明でも述べていますが、マイナンバーを利用した行政手続を行うためには、マイナンバーの提供だけでなく、本人の顔写真入りの本人確認書類等による「本人(身元)確認」を必ず行います。このため、マイナンバーの提供だけでは本人になりすまして行政手続を進めることはできません。
マイナンバー制度の下に、個人情報は一元的に管理されない
- 「マイナンバー制度の開始により、個人情報が一元的に管理される」というご懸念をいただくことがありますが、これは正確ではありません。
- マイナンバー制度開始後も、市役所における住民情報や税情報、日本年金機構における年金情報などの各行政機関が持つ情報は、これまで通り各行政機関等が保有しています。言い換えれば、マイナンバーを元に一つの行政機関により全ての個人情報が管理されるという状態は、制度上存在しません。(「一元管理」ではなく「分散管理」と表現されています。)
- 一方で、マイナンバー制度の開始により、行政機関は、住民からのマイナンバーを伴う手続の申請を起点として、手続上の必要に応じ、マイナンバーを元に異なる行政機関が保有する個人情報の確認ができるようになりました。これがマイナンバー制度でも説明した「情報連携」と呼ばれる仕組みになります。
「情報連携」の流れは、一方の行政機関が他方の行政機関に、その手続きに必要な個人情報のみを照会(提供を依頼)し、他方の行政機関が自身が持つ個人情報のみを回答(提供)するというものであり、この点でもいわゆる「一元管理」とは言えない性質のものですが、安全性をより確実に担保するため、マイナンバーそのものを使って「情報連携」を行わないような仕組みとなっています。
具体的には、マイナンバーを伴う手続の申請により行政機関に提供された、または行政機関がマイナンバーと共に保有する個人情報はそのまま使われず、まず行政機関内で暗号化された符号(機関別符号)と紐付けられます。
この「機関別符号」は行政機関同士で異なる符号となっていますが、この符号同士がデジタル庁が運営する行政機関専用のネットワークである「情報提供ネットワークシステム」内で紐付けられることにより、異なる行政機関同士で同じ人の個人情報を安全に連携させることが可能になるだけでなく、悪意のある人が他人のマイナンバーを不正に取得し、ある行政機関から他の行政機関が持つ個人情報を一元的に集めようしても、「情報ネットワーク」にアクセスできるのは限られた行政機関の職員のみであることから、「情報連携」の起点となる「機関別符号」の取得は困難であり、かつ他の行政機関の「機関別符号」は、マイナンバーだけでは類推が不可能であるため、さらに取得が困難です。
以上のような対策が、「仮にマイナンバーが漏えいしても、住民の情報を芋づる式に(一元的に)抜き出すことはできない。」とされる根拠の一つとなっています。 - 以下のリンク先に「分散管理」や「情報連携」の模式図が添付されていますので、こちらも参考までにご覧ください。
マイナンバー制度におけるシステム面の安全対策(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナポータルを通じて、行政機関同士でやりとりされる自分の情報のチェックができる
- デジタル庁が運営する「マイナポータル」(新しいウインドウが開きます)内の「やりとり履歴」のメニューから、どの行政機関において、いつ、どのように「情報連携」がされたのか、ご自身でチェックすることができます。
やりとり履歴について|マイナポータル(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
- マイナポータルでは、「わたしの情報」というメニューから、各行政機関が保有する自分の個人情報をマイナンバー制度に基づく情報連携と同じように取得することもできます。
わたしの情報について | マイナポータル(デジタル庁が運営)(新しいウインドウが開きます)
- マイナポータルそのものが、本人しか使えない「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書」及び「暗証番号」でしかログインができないため、「自分の個人情報は自分しかチェックできない」という安全性も同時に担保されており、かつ、「仮にマイナンバーが漏えいしても、(マイナンバーカードの電子証明書及び暗証番号によりマイナポータルにログインされない限り)住民の情報を芋づる式に(一元的に)抜き出すことはできない。」 といえます。
「個人情報保護委員会」によるチェック機能
行政機関からは独立した第三者委員会である「個人情報保護委員会」が、情報提供ネットワークシステムの監視や、行政機関等がマイナンバーを含む個人情報が適切に管理しているか監視・監督を行っています。
個人情報保護委員会について(個人情報保護委員会ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
罰則
申請の際に取得したマイナンバーや「情報連携」により得た情報を不正に提供・利用したり、盗用したりするなどの法令違反に対しては、拘禁刑をはじめとした厳しい罰則が科せられます。マイナンバーカードについても同様です。
制度面の安全対策(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードにおける安全対策
顔写真入りのカードや「券面情報」によるなりすましの防止
- 仮にマイナンバーカードを紛失しても、本人確認にマイナンバーカードの顔写真を利用することから、取得した第三者が容易になりすますことはできません。
- マイナンバーカードのICチップは偽造が困難であるため、ICチップに記録されている券面情報をマイナンバーカードの表面の情報と併せて確認することで、偽造されたマイナンバーカードの判別につながります。
- 1歳未満の住民が取得する「顔写真なしマイナンバーカード」は、そもそも本人確認書類として利用することができません。
マイナンバーカードのICチップに記録されている個人情報は「必要最小限」のもの
- マイナンバーカードのICチップに記録されている電子証明書は、暗証番号や顔認証を用いて本人が行政手続の際に利用することで初めて効力を発揮するものであり、単体では意味を持ちません。
- ICチップには券面情報、住民票コード、マイナンバーを含む券面事項も記録されていますが、これらの情報のうち顔写真や氏名、住所、生年月日、性別は、本人確認、行政手続きに必要な最小限度のものです。逆に言うと、これらの情報以外のいわゆる「機微情報」と呼ばれるような税情報や年金情報、健康診断情報や病歴、薬の処方履歴などの情報はICチップの中には一切入っておらず、マイナンバーカードを取得した第三者がICチップから取り出す事態は存在しません。
ただし、電子証明書と暗証番号を用いてマイナポータルにログインすることで、いわゆる機微情報の確認自体は可能であることから、万一暗証番号が漏えいした場合に悪用されることを防ぐため、マイナンバーカードを紛失した場合は直ちに電話での「一時停止」手続きを行う必要があります。
また、マイナンバー制度における安全性の説明とも重複しますが、これらの情報のうち住民票コードやマイナンバーについては、顔写真等による本人確認を伴わなければ行政手続きに利用することはできないため、この点においてもマイナンバーカードを取得した第三者がなりすましにより手続きを行うことは困難です。 - マイナンバーカードの健康保険証としての利用を例に挙げると、病院や薬局のカードリーダーでマイナンバーカードを読み取らせる際には、ICチップから保険証番号及び健康診断情報や病歴、薬の処方履歴を抜き出しているわけではなく、(そもそも記録されていません。)暗証番号の入力や顔認証による電子証明書の利用を通じて、その都度本人の情報提供意思を確認することにより、保険者(市役所や保険組合)が持つ保険情報や医療情報が、マイナポータルでの本人による情報の確認と同じように、病院や薬局にオンラインで提供されるという仕組みになっています。これは「オンライン資格確認」と呼ばれる仕組みであり、令和6年12月2日からの、いわゆる「マイナ保険証」の制度の本格運用開始に伴い整備された仕組みになります。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードのICチップには「耐タンパー」や「暗証番号ロック」などの自己防衛機能がある
- マイナンバーカードのICチップには、記録された情報を不正に読み出そうとすると、自らその記録を抹消し、二度と使えなくする仕組み(「耐タンパー」と呼ばれる機能)が備わっています。
- ICチップに記録された電子証明書の暗証番号やマイナンバーカードの暗証番号は、複数回入力を間違えるとロックがかかる仕組みとなっており、ロックの解除には本人が手続きを行うことを求めることで、不正利用の防止を図っています。
マイナンバーカードの安全性(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードの安全性資料(リーフレット)(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
紛失・一時停止/セキュリティ(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードのセキュリティ対策(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードをなくしたとき(一時停止と再発行手続)
マイナンバーカードにおける安全性でも説明したとおり、マイナンバーカードを紛失した場合は、カードそのもの利用したなりすましは困難であるものの、万一の暗証番号の漏えいによる電子証明書などの悪用を防ぐために、下記の「マイナンバー総合フリーダイヤル」への連絡によるカードの一時停止の手続を行う必要があります。
一時停止処理を行うことで、紛失したマイナンバーカードを第三者が取得しても、電子証明書などのマイナンバーカードの機能が利用できなくなるため、機能の悪用による二次被害の防止など、一定の安全性が確保されます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
- 音声ガイダンスで2番をお選びください。
- 一時利用停止の手続は24時間365日対応しており、一部の外国語にも対応しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
お電話でのお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
警察署等への遺失届
自宅以外の外出先等で紛失した場合は、最寄りの警察署や交番にて「遺失届(紛失届)」の提出手続(新しいウインドウが開きます)を行ってください。その際は、「受理番号」、「届け出た警察署や交番名」、「届け出た警察署や交番の電話番号」を控えてください。
マイナンバーカードの再発行手続
- マイナンバーカードの一時停止の手続をした後、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、本人が市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)に来庁し、一時停止解除の手続と電子証明書の再発行手続きを行うことができます。
- 紛失したマイナンバーカードが見つからず、マイナンバーカードを作り直したい場合は、本人が市役所市民課及び市民課芦原分室(あわら市保健センター内)に来庁し、新しいマイナンバーカードの再発行申請を行う必要があります。紛失に伴う再発行の際は、原則、以下に示す「再交付手数料」を納めていただかなければなりません。再交付手数料は「マイナンバーカード再交付手数料」と「電子証明書の再発行手数料」に分かれています。
なお、紛失に伴う再発行の際は、申請から1週間前後を目安に、マイナンバーカードを地方公共団体システム機構から本人の住所宛に直接「簡易書留」で送付する「特急発行申請」が利用できますが、紛失に伴う特急発行申請の場合は、「再交付手数料」が通常よりも増額となるため、必要性を勘案のうえどちらの発行方法をとるかを申請時にお選びください。
|
手数料の種類 |
通常の再発行の場合 | 特急発行を利用する場合 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード再交付手数料 | 800円 | 1,800円 |
| 電子証明書再交付手数料 | 200円 | 200円 |
| 合計 | 1,000円 | 2,000円 |
- 再発行手続を受け付けた後のマイナンバーカードの申請の流れや必要となる書類は、初めてマイナンバーカードを申請する場合と同じになります。
- 新しいマイナンバーカードの受け取り後に紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、紛失したマイナンバーカードはすでに廃止状態であるため返納いただくことになります。
なお、この時点ですでに有効なマイナンバーカードを発行していることから、再交付手数料の払い戻しはできません。 - 新しいマイナンバーカードでは、ICチップ内の電子証明書も新しいものに変わっているので、電子証明書を更新した場合と同じく、利用しているサービスのうち該当するものがある場合、そのサービスへの新しい電子証明書の登録や再申請が必要となります。
マイナンバーカードの安全性(詳細:紛失・盗難時の手続の案内があります。)(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
昨今発生している「マイナンバーの紐付け誤り」、「コンビニでの証明書の誤交付」、「なりすまし」などのトラブルはマイナンバーカードが原因ではありません
昨今発生している以下のようなトラブルについては、マイナンバー制度やマイナンバーカードに関連するものではありますが、マイナンバー制度やマイナンバーカード自体がトラブルの原因ではありません。
このため、 マイナンバー制度やマイナンバーカード自体の安全性は、現在も損なわれることなく保たれていますが、制度への信頼を損ねないよう、このようなトラブルは極力発生を予防する必要があります。
参考までに主なトラブルの事例を紹介します。
「マイナンバーの紐付け誤り」
マイナンバー制度に基づく情報連携やマイナンバーカードの健康保険証利用(新しいウインドウが開きます)のためには、本人からのマイナンバーを伴う申請を元に、行政機関内部でマイナンバーと個人情報とを紐付ける作業が行われますが、この作業が一部手作業で行われていたり、申請時にマイナンバーを取得せずに同姓同名の人を検索して紐付けるなど、アナログな対応が行われていたりしていました。
これは、申請時にマイナンバーを取得して、マイナンバーを元に個人を明確に特定したり、マイナンバーから情報連携に必要な符号を自動的に生成する仕組みを導入していれば防げた事例であり、マイナンバーやマイナンバーカードそのものの不具合とはいえないものでした。トラブルへの対応としては、届出へのマイナンバーの記載業務の明確化や、紐付け済みのデータ全体のチェックが行われました。
なお、あわら市では上記のトラブルは発生していません。
「コンビニでの証明書の誤交付」
証明書のコンビニ交付を利用して住民票を取得したところ、別人の住民票が交付されたという事例がありました。これは、ある事業者が提供するコンビニ交付システムでの証明書の印刷段階において、本来であれば全国からの交付申請を受け付けた順番に印刷を行われなればならないところ、申請件数の増加による負荷がかかったこともあり、証明書の印刷準備が早く出来た順に印刷を行ったため、ある人の交付申請を受け付けたマルチコピー機に、早く出来た別の人の証明書が印刷されるという結果を招いてしまいました。
コンビニ交付にはマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて本人確認を行いますが、この電子証明書を用いた本人確認の過程では不具合は生じていなかったにもかかわらず、上記のような設計上の不具合により誤交付が生じてしまった事例といえます。
なお、あわら市では上記の事例とは異なる事業者のコンビニ交付システムを導入しており、あわら市のコンビニ交付システムでは、設計上、上記の事例が発生しない(証明書は負荷にかかわらず交付申請を受け付けた順番に印刷される)ことを確認したほか、個別の点検も実施し、コンビニ交付システムの安全性が担保されていることを確認済みです。
「なりすまし」による不正な契約締結
偽造されたマイナンバーカードで不正な契約が行われた事件がありました。
使われた偽造マイナンバーカードはICチップまでは入っておらず、地方公共団体情報システム機構が提供するソフトウェア(新しいウインドウが開きます)などを用いてICチップ内の券面情報も併せて確認をしていれば、回避しうる事例でした。現在はスマートフォンにインストールして、より簡単に券面情報の確認ができる「対面確認アプリ」がデジタル庁から提供されたほか、マイナンバーカードの表面だけでなくICチップ内の券面情報と併せたより厳格な本人確認が推奨されるようになりました。
マイナンバーカード対面確認アプリ(デジタル庁が提供)(新しいウインドウが開きます)
なお、行政機関が行うマイナンバーカード関連の手続に際しては、国の指示に基づきICチップ内の券面情報も併せて確認することが当初から要請されています。
以下のリンク先も、参考までにご覧ください。
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーに便乗した詐欺にご注意ください
行政手続以外の場面での「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。 また、行政手続においても、電話やメールでマイナンバーの聞き取りを行うことはありません。不審な点を感じたら、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。
以下のリンク先もご覧ください。
マイナンバーに便乗した詐欺にご注意ください!!(市ホームページ)
マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバーカードの情報の変更(住所や氏名などが変わったとき)
マイナンバーカードの情報(券面記載事項、内部記録事項)の変更(書き換え)
転入、転居、婚姻などで、氏名、住所などの本人確認情報に変更があった場合には、市役所でマイナンバーカードの情報の変更(書き換え)を行う必要があります。書き換えにはマイナンバーカードのICチップに記録された(No.3)住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を利用します。
- 転入の場合で、届出やマイナンバーカードの持参が遅れるなどして以下に挙げる条件にどれか一つでも当てはまってしまうと、マイナンバーカードが廃止になり、情報の変更ができなくなってしまいます。この状態でマイナンバーカードの再発行を希望する場合は、紛失に伴う再発行と同じ扱いとなり、再交付手数料を納めていただかなければなりませんので、速やかに手続を行ってください。
- 市外(前住所)で転出届をした際に届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかった場合
- 市内の住所に住み始めてから14日を経過して転入届をした場合
- マイナンバーカードの情報の変更を行わないまま、転入届をした日から90日を経過した場合
- 本人以外の代理人による転入、転居の際は、代理人が本人と同一の世帯に属する人および法定代理人であれば、本人の(No.3)住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を用いて、マイナンバーカードの情報の変更を行うことができますが、本人と同一の世帯に属する人および法定代理人以外の代理人による情報の変更は手続当日に行うことはできません。電子証明書の更新手続のような「回答書兼委任状」の送付を介して、後日代理人が改めて手続を行うか、本人が後日市役所にお越しになり手続を行うことになります。
- 変更後の情報は、届出日と併せてマイナンバーカード表面の追記欄に印刷または記入押印されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人の転出、転入手続き (市ホームページ)
- 請求により住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードの情報も旧氏併記のものに変更できます。
マイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記(市ホームページ)
電子証明書(署名用電子証明書)の情報の変更(失効及び再発行)
マイナンバーカードの電子証明書のうち署名用電子証明書には、氏名、生年月日、性別、住所の情報が含まれるため、転入、転居、婚姻などで本人確認情報に変更があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。このため、署名用電子証明書を引き続き使うためには、マイナンバーカードの情報の変更(書き換え)に併せて、署名用電子証明書の変更(再発行)も行う必要があります。署名用電子証明書の変更には、(No.1)署名用電子証明書暗証番号(英大文字と数字を組み合わせた6文字以上16文字以下のもの)が必要です。
- マイナンバーカードの情報の変更の場合と異なり、署名用電子証明書暗証番号は本人の真正性を担保するものであることから、本人以外の代理人による署名用電子証明書の変更(再発行)は手続当日に行うことはできません。電子証明書の更新手続のような「回答書兼委任状」の送付を介して、後日代理人が改めて手続を行うか、本人が後日市役所にお越しになり手続を行うことになります。
- 15歳未満の人は原則署名用電子証明書が発行されないので、再発行手続は不要です。
- 電子証明書の更新手続にあるとおり、署名用電子証明書を再発行した場合は、スマホ用電子証明書の再登録も必要になります。
(証明書のコンビニ交付のうち「本籍地証明書交付サービス」)婚姻等により戸籍に変更があった場合
証明書のコンビニ交付のうち「本籍地証明書交付サービス」 (新しいウインドウが開きます) を利用している人で、婚姻などで戸籍に変更があった場合は、マイナンバーカードの情報(氏名など)に変更がない場合でも、新しい戸籍に利用者証明用電子証明書のシリアル番号を紐付ける必要があることから、電子証明書の更新と同じく、再度利用登録申請が必要になります。
日本国外での利用について(国外転出者向けマイナンバーカード)(令和6年5月27日開始)
マイナンバーカードを持っている日本国籍を持つ人は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して(国外転出者向けマイナンバーカードに変更して)利用できるようになりました。継続利用手続では、転入、転居と同様のマイナンバーカードの情報の変更に加えて、署名用電子証明書の情報の変更を伴う「電子証明書の更新(失効及び再発行)」を行います。必要となる暗証番号も更新時と同じになります。
- マイナンバーカード及び署名用電子証明書の住所は「国外転出 年月日(国外転出予定日)」に変更されます。
- 国外転出の場合は転入、転居、婚姻などの場合と異なり、一度国外転出が確定すると、マイナンバーカードが廃止(返納)状態となります。この場合は、転入とは異なり「日本国内の新しい住所」での変更処理ができなくなるため、国外転出後の継続利用もできなくなります。これを防ぐために、国外転出の手続は「実際に転出する日(異動日)」よりも前に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
具体的には、例えば国外への転出予定日(異動日)の前日(一日前)に転出手続をしていただくことで、手続をした日(つまり異動日の一日前)から異動日までの間はカードは廃止(返納)とならず、保留状態となります。この保留状態のカードの情報(住所)を「国外転出 年月日(国外転出予定日)」に変更(書き換え)を行い、併せて電子証明書の再発行を行うことで、異動日後も国外で継続利用ができるようになります。 - 帰国後は、転入と同じように、帰国先の市区町村で国外転出者向けマイナンバーカードの情報(住所)を日本国内のものへと変更(書き換え)し、併せて電子証明書の再発行を行います。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用(国外転出者向けマイナンバーカードへの変更) 手続の大まかな流れやその他の手続については、以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍を持つ人(2015年10月5日以降に国外転出をしている人に限る。)も、マイナンバーカード(国外転出者向けマイナンバーカード)を申請することが可能になりました。
- この場合の本人の住所は国外転出後のマイナンバーカードの継続利用と同様 「国外転出年月日(国外転出した日) 」となり、「日本国内で住所を特定する根拠にはならない」ため、これまでは国外在住者は(住所地で発行する)通常のマイナンバーカードを取得することはできませんでしたが、法改正により「住民基本台帳ネットワーク」を利用して、「戸籍(日本国籍)がある限り、住所が国外になっても戸籍ととともに残り続け、国内における住所が異動の度に記録される」性質を持つ「戸籍の附票」を、地方公共団体の間で連携させるようになったことにより、海外在住者の「戸籍」とともに「戸籍の附票」を保有する地方公共団体(本籍地市区町村。国外転出者向けマイナンバーカードの事務においては「附票管理市区町村」と定義されています。)が、住民基本台帳ネットワークを通じて海外在住者を特定し、国外転出者向けマイナンバーカードの申請を担うことができるようになりました。
- 国外在住者による国外転出者向けマイナンバーカードの申請や受け取りについては、本籍地市区町村(附票管理市区町村)以外の市区町村(帰国時の一時滞在地)や在外公館でも可能ですが、例えばあわら市に本籍が国外在住者については、国外転出前の住所や申請、交付を受け付ける市町村があわら市以外であっても、申請情報は必ず附票管理市区町村であるあわら市を経由して、戸籍の附票に基づき本人を特定した後、マイナンバーカードの発行主体である地方公共団体情報システム機構に引き渡されるという手続の流れになります。
国外在住者の国外転出後のマイナンバーカード(国外転出者向けマイナンバーカードへの変更)の申請、 交付の大まかな流れについては、以下のリンク先をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
住民基本台帳カードとの関係
住民基本台帳カード(住基カード)とは、マイナンバーカードの発行が開始される以前に「住基ネット(住民票コード)」を基盤としてに地方公共団体で発行を行っていたカードであり、顔写真入りの住基カードはマイナンバーカードと同様に、本人(身元)確認書類として利用が可能であり、公的個人認証制度に基づく電子証明書も住基カードの時点でICチップに搭載されていました。このため、住基ネットからマイナンバー制度に基づく情報連携に発展したように、マイナンバーカードもまた、社会の変化に応じて住基カードから発展したものといえます。
住基カードの発行は平成27年12月で終了し、令和7年(2025年)12月28日で全ての住基カードの有効期限も満了となったことにより、サービスを終了しました。なお、マイナンバーカードを取得する際は住基カードの返納が必要です。
住基カードをお持ちの方へ(総務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
よくある質問
- よくある質問:マイナンバーカード(市ホームページ)
- よくある質問|公的個人認証サービス(地方公共団体システム機構が運営)(新しいウインドウが開きます)
- よくある質問|マイナポータル(デジタル庁が運営) (新しいウインドウが開きます)
- よくある質問:個人情報の保護について(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
関連リンク
- マイナンバーカード出張申請受付について(職員がご自宅等に申請受付に伺います)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受け取り)について(代理人受け取りの対象者が拡大されました)
- 証明書のコンビニ交付について(夜間、休日でも証明書が取得できます)
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人の転出、転入手続き
- 住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記について
- マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
- 令和6年12月2日で保険証の新規発行がされなくなりますので、マイナ保険証をご利用ください!
- 「マイナ受付」ができる医療機関・薬局ではマイナンバーカードまたは資格確認書があれば限度額適用認定証等の提示が不要です
- マイナンバーに便乗した詐欺にご注意ください!!
- マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省ウェブサイト)(新しいウィンドウが開きます)
- マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ウェブサイト)(新しいウィンドウが開きます)
- マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体システム機構が運営)(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8014 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp